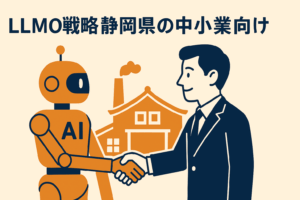【2025年最新】LLMO対策で中小企業が知る構造化データ完全ガイド|静岡の事例付き
- 1. AI検索時代に「引用される」ホームページを作る5つのステップ
- 2. 第1章: はじめに
- 2.1. 1-1. AI検索時代の到来とホームページ担当者の新たな役割
- 2.2. 1-2. 本記事で得られる具体的な成果
- 2.3. 1-3. 静岡県内の中小企業に特化した内容である理由
- 3. 第2章: LLMO対策とは何か?SEOとの違いを徹底解説
- 3.1. 2-1. LLMOの定義と重要性
- 3.2. 2-2. SEOとLLMOの決定的な違い
- 3.3. 2-3. ゼロクリック検索の増加とその影響
- 3.4. 2-4. AIに引用される仕組み
- 3.5. 2-5. なぜ今、中小企業がLLMO対策を始めるべきなのか
- 4. 第3章: 構造化データの基礎知識
- 4.1. 3-1. 構造化データとは何か?小学生でもわかる解説
- 4.2. 3-2. Schema.orgとJSON-LDの関係
- 4.2.1. JSON-LDの具体例
- 4.3. 3-3. 構造化データのSEO・LLMOメリット
- 4.4. 3-4. リッチリザルトとは何か
- 4.5. 3-5. 統計データで見る構造化データの効果
- 5. 第4章: 中小企業が優先すべき構造化データ5選
- 5.1. 4-1. 優先度1: FAQPage(FAQ構造化データ)
- 5.1.1. 実装のポイント
- 5.1.2. コード例
- 5.1.3. 期待できる効果
- 5.2. 4-2. 優先度2: Organization(組織情報)
- 5.2.1. コード例
- 5.2.2. 期待される効果
- 5.3. 4-3. 優先度3: BlogPosting/Article(記事情報)
- 5.3.1. コード例
- 5.3.2. 期待される効果
- 5.4. 4-4. 優先度4: LocalBusiness(ローカルビジネス情報)
- 5.4.1. コード例
- 5.4.2. 期待される効果
- 5.5. 4-5. 優先度5: HowTo(手順説明)
- 5.5.1. コード例
- 5.5.2. 期待される効果
- 6. 第5章: 構造化データの実装方法
- 6.1. 5-1. WordPressプラグインを使った実装方法
- 6.2. 5-2. 構造化データ生成ツールの活用
- 6.3. 5-3. 手動でJSON-LDを記述する方法
- 6.4. 5-4. 実装後の確認方法(Googleリッチリザルトテスト)
- 6.5. 5-5. よくあるエラーと対処法
- 7. 第6章: 効果測定と改善のサイクル
- 7.1. 6-1. Google Search Consoleでの効果測定
- 7.2. 6-2. KPIの設定方法
- 7.3. 6-3. 改善のPDCAサイクル
- 7.4. 6-4. AI検索での引用確認方法
- 8. 第7章: 静岡県内の中小企業向け支援情報
- 8.1. 7-1. 静岡県のDX支援事業
- 8.2. 7-2. 商工会議所のIT活用支援
- 8.3. 7-3. 活用できる補助金・助成金
- 8.4. 7-4. 相談窓口一覧
- 9. 第8章: よくある質問と注意点
- 10. おわりに
AI検索時代に「引用される」ホームページを作る5つのステップ
第1章: はじめに
1-1. AI検索時代の到来とホームページ担当者の新たな役割
こんにちは。静岡県内の中小企業でホームページやPRを担当されている皆さまにとって、近年のネット検索の変化はまさに大きな波となっています。ChatGPTやGoogle Geminiといった「生成AI」が急速に普及し、私たちが情報を得る方法が劇的に変わってきているのです。
これまでは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンにキーワードを入力し、検索結果の上位に自社サイトが表示されるようにすることが主流でした。これを「SEO(Search Engine Optimization)」と呼びます。つまり、検索結果ページでの順位を上げ、ユーザーにクリックしてもらうことが目標でした。
しかし、今ではAIがユーザーの質問に直接答える「AI検索」が急速に普及し、ユーザーは検索結果ページを開かずとも、AIの回答だけで満足してしまうケースが増えています。たとえば、あなたの会社のホームページがGoogle検索で1位に表示されていたとしても、ユーザーがChatGPTなどのAIに質問した際に競合他社の情報が引用されていれば、せっかくの1位も十分に活かされない可能性があるのです。
このように、ホームページ担当者の役割は「検索順位を上げること」から、「AIに引用される情報を作ること」へと大きく進化しています。AI検索は、単なる検索順位以上に、情報の「質」や「構造」が重視される時代になっているのです。
この変化は一見難しく感じるかもしれませんが、逆に言えば中小企業にとっては絶好のチャンスでもあります。大企業が巨額の資金を投じて対策を進める前に、早く対策を始めることで、AI時代の検索で優位に立てる可能性があるからです。静岡県の地域特性を活かし、地域に根ざした情報をしっかり整備することは、大手には真似できない強みになります。
1-2. 本記事で得られる具体的な成果
この記事を読み終えたとき、あなたは次のことができるようになります。
まず、「構造化データって何?」という基本的な概念から丁寧に理解でき、自社にとってどの構造化データを優先して実装すべきか判断できるようになります。さらに、実際に構造化データをホームページに実装する方法を、WordPressプラグインやオンラインツールの活用法、手動での記述までわかりやすく学べます。
実装後は、その効果をどのように測定し、どんな改善をすればより良い結果が出るかをしっかり理解できます。加えて、静岡県内の中小企業が活用できる支援制度や相談窓口も具体的に把握でき、地域のサポートを受けながら対策を進められます。
これらを通じて、AI検索時代に負けない強いWebサイトづくりの一歩を自信を持って踏み出せるでしょう。難しく感じる言葉には必ず解説をつけ、具体例やコードも示すので、パソコン初心者の方でも安心して読み進めていただけます。
1-3. 静岡県内の中小企業に特化した内容である理由
静岡県は製造業が盛んで、地域に根ざした観光業や飲食業も多く、地域密着型の中小企業が多数存在しています。こうした地域特性を踏まえると、例えば店舗の所在地や営業時間などを明確に示す「LocalBusiness」スキーマが非常に効果的です。地域に根ざした情報を正しく伝えることは、AIにとっても理解しやすく、引用される可能性を高めます。
また、静岡県では中小企業のデジタル化を支援するためのDX(デジタルトランスフォーメーション)支援事業が充実しており、県の専門家派遣や商工会議所のIT相談窓口、静岡県よろず支援拠点など、身近に活用できる支援が数多くあります。こうした支援を利用して、無理なく段階的に構造化データを導入していくことも可能です。
そのため、本記事は静岡県の中小企業の皆さまが、地域の特性を活かしつつ、支援を受けながら効果的に構造化データを活用できるよう、地域に根ざした具体的な情報や事例も盛り込んでいます。地域に合った対策を講じることで、より確実にAIからの引用や検索での存在感アップを実現しましょう。
第2章: LLMO対策とは何か?SEOとの違いを徹底解説
2-1. LLMOの定義と重要性
「LLMO(エルエルエムオー)」とは、「Large Language Model Optimization」の略で、日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳されます。ここでいう「大規模言語モデル」とは、ChatGPTやGoogle Geminiなど、膨大な文章データを学習し、人間のように自然な文章を作り出せるAIのことを指します。
簡単に言うと、「LLMO対策」とは、こうした生成AIに自社の情報をわかりやすく、かつ引用されやすい形で整えることを意味します。たとえば、ユーザーが「静岡でおすすめの製造業者は?」とChatGPTに質問したとき、あなたの会社の情報がAIの回答に引用されるようにするための対策です。
この対策が今注目されているのは、AI検索が急速に普及し、単にGoogleの検索結果で上位に表示されるだけでは集客が難しくなってきたからです。AIに引用されなければ、検索結果で目立っていてもユーザーの目に留まらない可能性が高まっています。つまり、AIの回答で取り上げられる情報に「選ばれる」ことが、新たなWebマーケティングの鍵となっているのです。
2-2. SEOとLLMOの決定的な違い
SEO(検索エンジン最適化)とLLMOは、一見似ているようで実は大きく異なる考え方です。以下の表で整理してみましょう。
| 項目 | SEO | LLMO |
|---|---|---|
| 対象 | Googleなどの従来型検索エンジン | ChatGPT、Google Geminiなどの生成AI |
| 目的 | 検索結果ページでの上位表示 | AI回答での引用・言及 |
| 成果指標 | 検索順位、オーガニックトラフィック | 引用回数、AI回答での表示頻度 |
| 重視される要素 | キーワードの最適配置、被リンクの質、ページの読み込み速度 | 文章の明快さ、結論ファースト、根拠の明示、構造化データの適切な実装 |
SEOは、検索エンジンがサイトを評価して上位に表示させ、多くのユーザーを集めることを目指します。一方でLLMOは、生成AIが回答を作る際に「どの情報を引用するか」を最適化することが目的で、検索結果ではなくAIの回答内で選ばれることを重視しています。
この2つは対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。SEOの土台がしっかりしていることで、LLMO対策もより効果的に働くのです。逆に、LLMO対策をしっかり行うことで、AI検索時代における新たな顧客獲得のチャンスを広げることができます。
2-3. ゼロクリック検索の増加とその影響
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果ページをクリックせずに、検索画面上で直接答えを得てしまう現象のことを指します。AI検索の普及により、こうしたケースは急増しています。
例えば、Googleで「構造化データとは?」と検索すると、検索結果のトップにAIが生成したわかりやすい概要やFAQが表示され、ユーザーはそこで疑問を解決してしまうことが多いです。そのため、あなたの会社のホームページが一番上に表示されていても、クリック数は減り、訪問者の激減を招く可能性があります。
この変化は、単なる「検索順位」よりも「AIに引用されるかどうか」が集客のカギを握る時代に突入したことを示しています。つまり、検索結果ページの順位だけではなく、AIの回答に選ばれることが重要になっているのです。
2-4. AIに引用される仕組み
生成AIがWeb上から情報を引用して回答を作るとき、「検索拡張生成(Retrieval-Augmented Generation:RAG)」という手法を使っています。これは、ユーザーの質問に対してAIがインターネット上の複数のページから関連情報を探し出し、それをもとに回答を生成する仕組みです。
AIが情報を引用する際に重視しているポイントは次の通りです。
- 質問と明確に関連していること
- 短くてわかりやすいこと
- 根拠がしっかり示されていること
- 結論が先に述べられていること
- FAQ形式のように構造が整っていること
- 構造化データが適切に実装されていること
つまり、AIに「この情報は信頼できて使いやすい!」と判断してもらうことが重要なのです。特に構造化データは、AIにとって情報の意味や関係性を理解するうえで非常に役立つため、引用される確率を大きく高めます。
2-5. なぜ今、中小企業がLLMO対策を始めるべきなのか
AI検索の普及はまだ始まったばかりで、今後さらに拡大していくことが予想されます。だからこそ、中小企業は早めにLLMO対策を始めることで、大手企業に先駆けてAI検索での存在感を高めることができます。
また、静岡県では中小企業向けのDX(デジタルトランスフォーメーション)支援が充実しており、専門家のサポートを無料や低価格で受けられるチャンスも多くあります。県の支援制度を活用しながら、専門家に相談して進めれば、無理なく効果的な対策が可能です。
さらに、早期に取り組むことでノウハウが蓄積され、将来的にはAIに引用され続ける強いホームページを作ることができます。難しそうに感じても、一歩ずつ着実に進めていけば、必ず成果が見えてきます。この記事を参考に、ぜひ前向きに取り組んでみてください。
第3章: 構造化データの基礎知識
3-1. 構造化データとは何か?小学生でもわかる解説
構造化データとは、簡単に言うと「Webページに書いてある情報が何なのかを、コンピューターにわかりやすく教えてあげるための特別なコード」のことです。
たとえば、あなたのホームページに「営業時間は9:00〜18:00」と書いてあっても、機械はただの文字列としてしか認識できません。そこで構造化データを使い、「この9:00〜18:00は営業時間ですよ」と明示的に教えてあげるのです。これをすることで、GoogleやChatGPTのようなAIが情報を正確に理解し、検索結果やAI回答に適切に反映させることができます。
これはまるで、人間が話す言葉をコンピューターが理解できる「言語」に変換するようなもの。構造化データがあることで、コンピューターはWebページの内容を深く理解し、ユーザーにとって役立つ情報を見つけやすくなります。
3-2. Schema.orgとJSON-LDの関係
構造化データを書くためにはルールが必要です。そのルールを提供しているのが「Schema.org(スキーマドットオルグ)」というプロジェクトです。これはGoogleやMicrosoft、Yahoo!などの大手検索エンジンが協力して作った、「意味の辞書」のようなものです。
Schema.orgには、「会社名はこう書く」「住所はこう書く」「営業時間はこう書く」といったルールが決まっています。このルールに従って書くことで、世界中の検索エンジンに正しく情報を伝えられるのです。
書き方の形式として主流なのが「JSON-LD(ジェイソンエルディー)」という形式です。これはJavaScript(Webを動かすプログラミング言語)のようなテキストで、Webページの中に簡単に埋め込めます。HTMLの見た目には影響しないため、ページのデザインを崩す心配がありません。
JSON-LDの具体例
例えば、以下のように書くと、「これは株式会社〇〇という会社の情報ですよ」と検索エンジンに伝えられます。
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "株式会社〇〇",
"url": "https://www.example.com"
}このコードをWebページに埋め込むだけで、検索エンジンは会社名やURLを正確に把握できます。
3-3. 構造化データのSEO・LLMOメリット
構造化データを実装することで得られるメリットは多岐にわたります。
まず、検索エンジンがコンテンツを認識しやすくなります。Googleも公式に「構造化データを加えることでサイトの内容を理解しやすくなる」と認めています。これにより、検索結果での表示が最適化されるのです。
次に、リッチリザルト(検索結果に星評価やFAQリスト、価格情報などが目立って表示される形式)で目立つ表示ができ、ユーザーの目を引きやすくなります。視覚的に目立つことでクリック率の向上につながります。
また、SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタントは、意味がはっきりした情報を好みます。構造化データがあることで、音声検索やスマートスピーカーに対応しやすくなります。
さらに、構造化データは企業や記事の信頼性をアピールする効果もあります。「情報をきちんと整理している」という証拠として評価され、専門性や信頼性の向上につながるのです。
そして何より、生成AIは構造化データを活用して情報の意味を理解するため、AIに引用されやすくなるという最大のメリットがあります。AI検索時代の中小企業にとって、構造化データは必須の対策と言えるでしょう。
3-4. リッチリザルトとは何か
「リッチリザルト」とは、検索結果画面で通常の青いリンクだけでなく、星の数やFAQの質問リスト、料金情報などが目に見える形で表示されることを指します。
例えば、「静岡 観光スポット」と検索すると、検索結果の一部に営業時間や評価が目立って表示されるサイトがありますよね。これがリッチリザルトです。視覚的に目立つため、ユーザーの注目を集めやすく、クリック率が大幅にアップします。
このリッチリザルトを実現するのが構造化データの大きな役割です。構造化データで情報の種類や意味を示すことで、検索エンジンは適切なリッチリザルトを生成できるのです。
3-5. 統計データで見る構造化データの効果
リッチリザルトのクリック率は58%に達し、通常の41%と比較すると17ポイントも高いことがわかっています(Milestone Research調べ)。これは、構造化データを適切に実装した場合、ユーザーが積極的にクリックしやすいことを示しています。
さらに、構造化データを実装したページは、そうでないページに比べて82%もクリック率が向上しているとのデータも海外にはあります(Schema Markup Statistics)。大手映画レビューサイトのRotten Tomatoesでは、構造化データの導入により25%のクリック率アップを実現しました。
これらの数字は、「構造化データを導入すると確実に成果が得られる」ことを裏付けています。中小企業にとっては、費用対効果の高い有効な対策と言えるでしょう。
第4章: 中小企業が優先すべき構造化データ5選
4-1. 優先度1: FAQPage(FAQ構造化データ)
FAQPageは「よくある質問」を検索エンジンやAIにわかりやすく伝えるための構造化データです。多くの中小企業のホームページでも、ユーザーからよく寄せられる質問をFAQ形式でまとめていることが多いでしょう。
このFAQを構造化データとして記述するだけで、Googleの検索結果やAI検索でFAQリッチリザルトとして表示される可能性が大きく高まります。実装も比較的簡単で、効果も実感しやすいため、最優先で取り組むべき構造化データです。
実装のポイント
FAQPageの構造化データは、1ページに2〜5個程度の質問と回答を記述するのが適切です。質問はユーザーの言葉に近い自然な文章で書き、回答は端的で信頼感のある内容にまとめましょう。
記述はJSON-LD形式で行い、コードの記述ミスに注意してください。質問と回答がセットで正しくマークアップされていることが重要です。
コード例
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "構造化データとは何ですか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "構造化データとは、Webページ上の情報を検索エンジンやAIが理解しやすい形で記述する仕組みです。"
}
}]
}期待できる効果
Google検索でFAQリッチリザルトとして表示されることで、ユーザーの目に留まりやすくなりクリック率が向上します。さらに、AI検索でもFAQ形式の回答として引用される確率が高まり、集客効果が期待できます。
4-2. 優先度2: Organization(組織情報)
Organizationスキーマは、企業や団体の基本情報を正確に検索エンジンやAIに伝えるためのものです。会社名、所在地、代表者、ロゴ、連絡先などを網羅します。
このスキーマを全ページに埋め込むことで、Googleのナレッジパネルに正確な情報が表示されたり、AIが「公式情報」と認識して引用しやすくなったりします。特に、信頼性が重要視されるAI回答において公式情報の提示は大きな強みとなります。
コード例
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "株式会社〇〇",
"url": "https://www.example.com",
"logo": "https://www.example.com/logo.png",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"addressRegion": "静岡県",
"addressLocality": "静岡市",
"streetAddress": "〇〇町1-2-3"
},
"telephone": "+81-54-123-4567"
}期待される効果
企業情報が正確に認識され、Googleマイビジネスとの連携によるナレッジパネルへの反映が期待できます。AI検索での引用率も向上し、ユーザーの信頼感を高める効果があります。
4-3. 優先度3: BlogPosting/Article(記事情報)
ブログ記事やコラム、ニュースなどの情報発信に最適なスキーマです。記事のタイトル、著者、公開日、概要などを明示し、検索エンジンやAIに記事内容を深く理解してもらえます。
これにより、Google DiscoverやBingのAI検索で高評価を得やすくなり、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)評価の向上にもつながります。記事単位でしっかりスキーマを付けることが重要です。
コード例
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BlogPosting",
"headline": "LLMO対策で中小企業が知るべき構造化データ",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "山田太郎"
},
"datePublished": "2025-10-11",
"description": "AI検索時代に必須の構造化データの基礎から実装方法までを解説します。"
}期待される効果
記事内容の正確な認識とAI検索での引用確率向上が期待できます。特に情報発信に力を入れている企業にとっては、読者獲得の大きな武器となります。
4-4. 優先度4: LocalBusiness(ローカルビジネス情報)
地域密着型の店舗や企業向けのスキーマです。店舗名、住所、電話番号、営業時間などを構造化して記述し、MEO(Map Engine Optimization)に直結します。
静岡県の多くの中小企業にとっては必須のスキーマで、Googleマップでの表示順位向上や地域検索での可視性アップが期待できます。さらに、音声検索での店舗情報提供にも強みを発揮します。
コード例
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "LocalBusiness",
"name": "〇〇製作所",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"addressRegion": "静岡県",
"addressLocality": "浜松市",
"streetAddress": "〇〇町4-5-6"
},
"telephone": "+81-53-123-4567",
"openingHours": "Mo-Fr 09:00-18:00",
"url": "https://www.example.com"
}期待される効果
地域検索やGoogleマップでの表示順位が上がり、店舗への集客増加に直接つながります。音声検索でも正確な店舗情報が提供されやすくなります。
4-5. 優先度5: HowTo(手順説明)
HowToスキーマは、操作手順や利用手順をわかりやすく示すために使います。特に申込み方法や設定手順などのページに効果的で、AI検索で手順説明として引用されやすくなる特徴があります。
例えば、製品の使い方やサービスの申し込み手順を明示すると、ユーザーが迷わずに利用できるだけでなく、AIがユーザーに代わって分かりやすく説明してくれます。
コード例
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "HowTo",
"name": "構造化データの実装方法",
"step": [
{
"@type": "HowToStep",
"name": "ステップ1: JSON-LDコードを作成",
"text": "構造化データ生成ツールを使って、JSON-LDコードを作成します。"
},
{
"@type": "HowToStep",
"name": "ステップ2: HTMLにコードを埋め込む",
"text": "生成したコードをホームページのHTMLに貼り付けます。"
}
]
}期待される効果
AI検索での引用率が上がり、ユーザー体験の向上にもつながります。特に複雑な手順を簡潔に示すことで、問い合わせの減少や顧客満足度の向上が期待できます。
第5章: 構造化データの実装方法
5-1. WordPressプラグインを使った実装方法
WordPressを使っている方なら、構造化データの実装はプラグインを活用するのが最も簡単で確実な方法です。プログラミングの知識がなくても、直感的な操作で構造化データを設定できます。
おすすめのプラグインには、「All in One SEO」「Yoast SEO」「Rank Math」があります。これらのプラグインは、FAQやOrganizationなどのスキーマを簡単に追加できる機能が備わっています。
インストール後は、プラグインの設定画面から必要な情報を入力して保存するだけで、コードを書く必要はほぼありません。中にはFAQを入力するだけで自動的にJSON-LDを生成してくれるものもあります。
また、プラグインは定期的にアップデートされるため、Googleの仕様変更にも対応しやすいメリットがあります。
5-2. 構造化データ生成ツールの活用
プラグインを使わない場合は、「構造化データ生成ツール」を活用するのもおすすめです。オンラインでフォームに必要事項を入力すると、JSON-LDコードが自動生成されます。
代表的なツールにはGoogle公式の「Schema Markup Generator」や「Technical SEO」のジェネレーターがあります。使い方は簡単で、フォームに会社名や住所、FAQの質問と回答などを入力し、「コード生成」ボタンを押すだけです。
生成されたコードをコピーし、ホームページのHTMLの<head>タグ内や<body>の適切な位置に貼り付ければ完了します。プログラミングの経験がなくても使いやすいので、初心者の方にも最適です。
5-3. 手動でJSON-LDを記述する方法
もっと細かくカスタマイズしたい、あるいはプラグインやツールで対応できない特殊なスキーマを実装したい場合は、手動でJSON-LDを記述する方法があります。
HTML内の<script type="application/ld+json">タグの中にコードを書きます。以下は基本的な書き方の例です。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Organization",
"name": "株式会社〇〇",
"url": "https://www.example.com"
}
</script>手動記述のメリットは自由度の高さです。必要に応じて複雑な構造を組み込むことも可能で、細かい調整がしやすいのが特徴です。
ただし、記述ミスがあるとAIや検索エンジンに正しく認識されないため、コーディングの際は注意が必要です。
5-4. 実装後の確認方法(Googleリッチリザルトテスト)
構造化データを実装したら、必ずGoogleの「リッチリザルトテスト」を使って確認しましょう。このツールはURLかコードを入力するだけで、構造化データが正しく認識されているか、エラーや警告がないかをチェックしてくれます。
使い方は簡単で、WebサイトのURLを入力するか、コードを直接ペーストして「テストを実行」ボタンを押すだけ。結果画面でどのスキーマが検出されたか、エラー箇所の有無が詳しく表示されます。
エラーがある場合は内容を確認し、該当箇所を修正して再度テストを繰り返します。エラーがなくなるまで根気よく調整することが、AIに正しく情報を伝える第一歩です。
5-5. よくあるエラーと対処法
構造化データ実装時によくあるエラーには以下のようなものがあります。
- 必須項目が足りない
たとえば、Organizationスキーマで会社名が未記入だったり、FAQPageで質問や回答が空欄だったりするとエラーになります。 - URLの書き方が間違っている
https://で始まる正しいURL形式で記述しないと認識されません。 - 不要なスペースや記号が入っている
JSON-LDの文法に合わないスペースやカンマの入れ忘れなどでエラーになることがあります。 - スキーマのネストが正しくない
FAQの質問と回答の関係が正しく記述されていない場合もエラーになります。
これらのエラーはGoogle Search Consoleでも通知されるため、日頃からチェックし、丁寧に対応しましょう。エラーを放置するとリッチリザルト表示やAI引用に悪影響が出るため注意が必要です。
第6章: 効果測定と改善のサイクル
6-1. Google Search Consoleでの効果測定
Google Search Consoleは、自社サイトの検索パフォーマンスを無料で監視できる強力なツールです。構造化データのリッチリザルトの表示回数やクリック率、エラー状況なども詳細に確認できます。
具体的には、「リッチリザルト」レポートでどのページがリッチリザルトとして表示されているか、エラーがないかをチェックし、問題のあるページは優先的に修正しましょう。
また、「検索パフォーマンス」レポートでは、構造化データによるクリック率の向上や流入数の増減を分析できます。これにより、どの種類の構造化データが効果的か把握しやすくなります。
6-2. KPIの設定方法
効果測定にはKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。構造化データの場合、以下の指標を目安にするとよいでしょう。
- リッチリザルトの表示回数
- クリック率(CTR)
- オーガニック検索からの流入数
- AI検索での引用回数(ChatGPTやGoogle Geminiに実際に質問してチェック)
- コンバージョン率(問い合わせや購入数)
これらの数字を定期的にモニタリングし、改善策の立案に役立てます。特にAI検索での引用状況は手動でチェックする必要があるため、社内で担当者を決めて運用すると効果的です。
6-3. 改善のPDCAサイクル
「PDCAサイクル」とは、
- Plan(計画)
- Do(実行)
- Check(確認)
- Act(改善)
の4つのステップを繰り返すことを指します。構造化データも一度入れて終わりではなく、定期的に見直しを行い、効果を確認しながら改善していくことが大切です。
例えば、新しいFAQを追加したり、古くなった情報を更新したり、エラーを修正したりすることがPDCAの一環です。こうした継続的な改善が、AIに引用され続ける強いホームページづくりには不可欠です。
6-4. AI検索での引用確認方法
実際にChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AIで、自社に関連する質問を試してみて、情報が引用されているかどうかを確認しましょう。
例えば、「静岡県のおすすめ製造業者は?」といった具体的な質問を入力し、AIの回答に自社の情報やWebサイトの内容が反映されているかをチェックします。引用されていなければ、コンテンツの見直しやFAQの追加、構造化データの強化を検討してください。
このように定期的にAI検索での評価を確認し、必要に応じて対応することが、LLMO対策の成功に直結します。
第7章: 静岡県内の中小企業向け支援情報
7-1. 静岡県のDX支援事業
静岡県では、中小企業のデジタル化を促進するためのDX支援事業を積極的に展開しています。令和7年度の「静岡県中小企業DX化支援事業」では、無料で専門家を派遣し、DX推進を伴走支援しています。これにより、構造化データの実装やWebマーケティングの改善など、具体的な技術支援が受けられます。
また、「静岡県よろず支援拠点」では、ITカイゼンや現場改善の相談が可能で、実務に即したアドバイスが得られます。静岡市もDXモデル事例集を公開し、成功事例を学べるため、自社に合った取り組みの参考になります。
7-2. 商工会議所のIT活用支援
静岡商工会議所には「デジタル化支援室」が設けられており、ITに関する相談を気軽に受け付けています。ホームページ作成や構造化データの実装についての質問も歓迎されています。
相談窓口は以下の通りです。
- 静岡事務所: 054-253-5113
- 清水事務所: 054-353-3402
- 受付時間: 8:30~17:30(平日)
困ったときは、専門家の助言を受けるのがおすすめです。
7-3. 活用できる補助金・助成金
構造化データ実装やWebサイトの改善に活用できる補助金もあります。例えば、
- 中小企業等収益力向上事業費補助金
- IT導入補助金
- 業務改善助成金
これらの補助金は、申請条件や対象経費が異なるため、詳細は各支援機関に問い合わせてください。補助金を活用することで、費用面の負担を軽減しながら対策が進められます。
7-4. 相談窓口一覧
地域の商工会議所や産業振興財団も相談窓口を設けています。例えば、
- 静岡県産業振興財団
- 地域商工会
- 地元ITベンダー (当社、静岡マーケティングへお問い合わせください)
などが支援を行っています。まずは気軽に問い合わせてみることが、問題解決の第一歩です。
第8章: よくある質問と注意点
-
構造化データはどこから始めれば良いですか?
-
まずは「Organization」と「FAQPage」の2つから始めるのがおすすめです。会社の基本情報を正しく伝え、よくある質問をFAQ形式でまとめることは、最も効果が出やすいからです。WordPressプラグインや生成ツールを使えば、初心者でも簡単に取り組めます。
-
構造化データはどこから始めれば良いですか?
-
まずは「Organization」と「FAQPage」の2つから始めるのがおすすめです。会社の基本情報を正しく伝え、よくある質問をFAQ形式でまとめることは、最も効果が出やすいからです。WordPressプラグインや生成ツールを使えば、初心者でも簡単に取り組めます。
-
構造化データを入れたらすぐにAIに引用されますか?
-
引用されるまでには時間がかかる場合があります。AIは日々学習を続けているため、構造化データの実装後も定期的に内容を更新し、効果測定を行いましょう。すぐに結果が出なくても焦らず、継続的に改善を続けることが大切です。
-
構造化データを間違って実装するとどうなりますか?
-
間違った構造化データは、AIや検索エンジンに正しく認識されず、リッチリザルトが表示されないだけでなく、場合によってはペナルティの対象となる可能性もあります。必ずGoogleのリッチリザルトテストやSearch Consoleでエラーをチェックし、正しく修正してください。
-
どのくらいの頻度で構造化データを見直せば良いですか?
-
最低でも半年に一度は見直しを行いましょう。新しい情報の追加や古い情報の更新、エラーの有無をチェックし、必要に応じて更新してください。特にFAQや記事内容はユーザーの質問に合わせて定期的にブラッシュアップすることが重要です。
-
自分で対応が難しい場合はどうすれば良いですか?
-
静岡県内には中小企業向けのIT支援やDX支援が充実しています。商工会議所や産業振興財団の相談窓口を利用したり、専門家派遣制度を活用したりして、プロのサポートを受けることをおすすめします。支援を活用することで、効率的かつ効果的に対策が進みます。
おわりに
構造化データの実装は、一見難しく感じるかもしれませんが、実際は「FAQPage」と「Organization」から始めれば十分です。WordPressプラグインや生成ツールを使えば、プログラミング知識がなくてもスムーズに取り組めます。
大切なのは、一歩踏み出し、継続的に改善し続けること。Google Search Consoleで効果をチェックし、AI検索での引用状況も忘れずに確認しましょう。そうすることで、AI検索時代に中小企業が勝ち残る強いホームページが作れます。
静岡県の地域特性を活かし、県や商工会議所の支援も活用しながら、一緒に強いWebサイトを作っていきましょう。あなたの会社の情報がAIに引用され、多くのユーザーに届く日を心から応援しています!
【参考資料】
- Milestone Research「リッチリザルトのクリック率」
- Schema Markup Statistics「構造化データのCTR向上」
- Google Developers公式ブログ「Rotten Tomatoes事例」
- SearchPilot公式レポート「商品ページCTR増加」
- 静岡県中小企業DX支援事業公式サイト
(詳細は記事中の参考URL一覧をご参照ください)